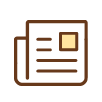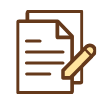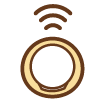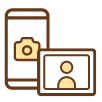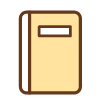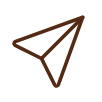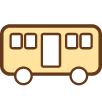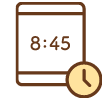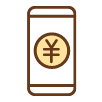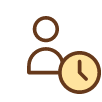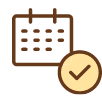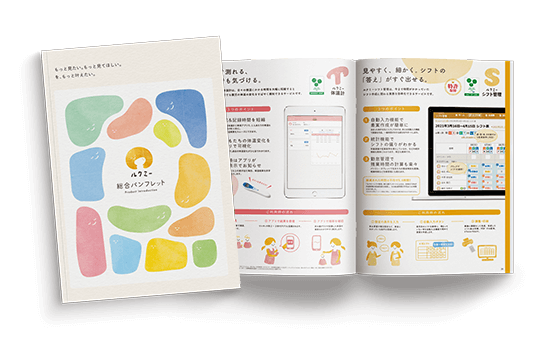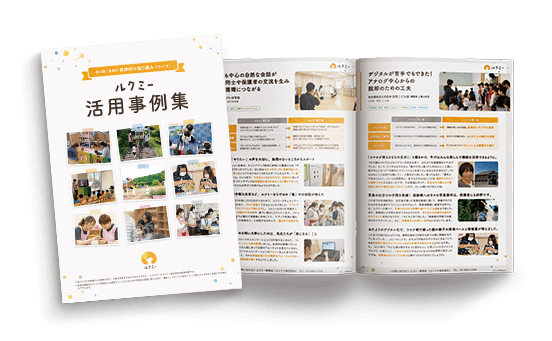保育AIで実現できた本来の「やりたい保育」への道

はじめに
近年、保育業界ではICTやAI技術の導入が進み、保育者の業務効率化や保育の質の向上に貢献しています。本コラムでは、ルクミーを導入された保育施設の事例を通して、ICTや保育AIによる効果や保育現場の変化についてご紹介します。
今回は、アソシエ都立大学保育園の古林(こばやし)先生にお話を伺いました。
ルクミー導入前の課題とICTやAIへの期待について
古林先生:以前の職場ではICTを導入しておらず、連絡帳も手書きだったため、保育現場のICT化が進むことに最初は戸惑いがありました。本当に便利になるのか、保護者に受け入れられるのかなど、ICTに対して漠然とした不安があったのが正直な気持ちです。
しかし、今の園に来た時、写真業務の効率化が喫緊の課題でした。写真管理業務では、二重チェックや手動での園児の写りのばらつきチェックに多くの時間がかかり、かなりの負担でした。
そこで、これらの業務課題を解決するためのツールとしてルクミーフォトを導入しました。特に、保育AI機能の「自動写真チェック」や「ばらつきチェック」に注目しました。
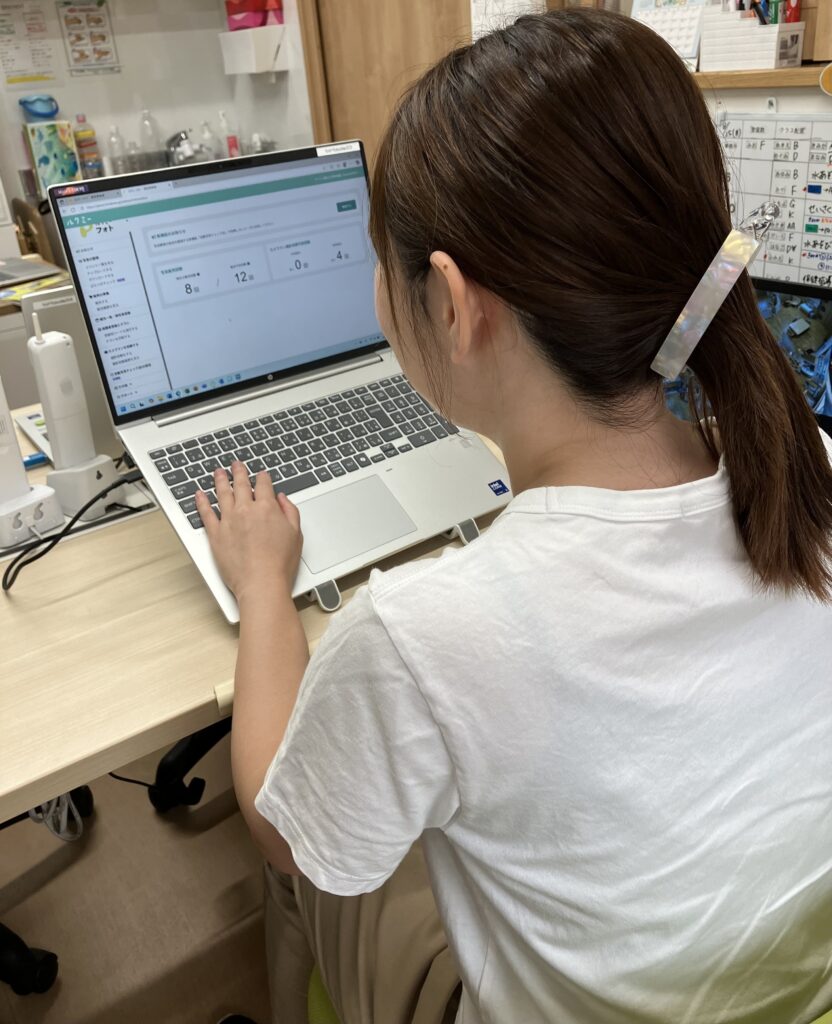
ルクミー導入時の工夫と写真業務の変化
古林先生:ルクミー導入時には、オンラインでの説明会が開催され、職員と園長が参加しました。当初は導入の難しさを感じた職員もいましたが、使い始めるうちにすぐに便利さを実感し、特に問題なく利用できるようになりました。
スマートフォンで撮影した写真が自動でタブレットに転送され、クラスごとに整理できるようになったため、写真を振り分ける作業負担は大幅に軽減されました。また写真共有もスムーズになり、保育者同士で他のクラスの写真がすぐに確認できたり、必要な写真をダウンロードして使用することもできるようになりました。
「自動写真チェック」も、保育者の業務を大きくサポートしてくれています。AIがブレた写真などを自動的に除外してくれるため、先生たちの確認作業は非常に楽になりました。また、写真掲載でNGとなっている園児の写真をAIがチェックすることで、誤って販売されることがなくなり、現場での確認作業が格段に減ったのは大きなメリットです。
保育AIは保育者の『やりたい保育』を実現する
古林先生:保育AI導入の価値は、保育者が「こどもと向き合う時間」を増やすことにあると思います。先生たちがパソコンに向き合う時間を短縮できたことで、その分こどもと向き合う時間が増え、企画を考えられるようになりました。年長児の地域交流や、インタビューを通じた新聞作成など、保育者が本来『やりたい保育』を実現するための時間が増えたと感じています。

お見積もりやサービス詳細など
お気軽にお問い合わせください
1〜3営業日以内に
担当よりご連絡いたします